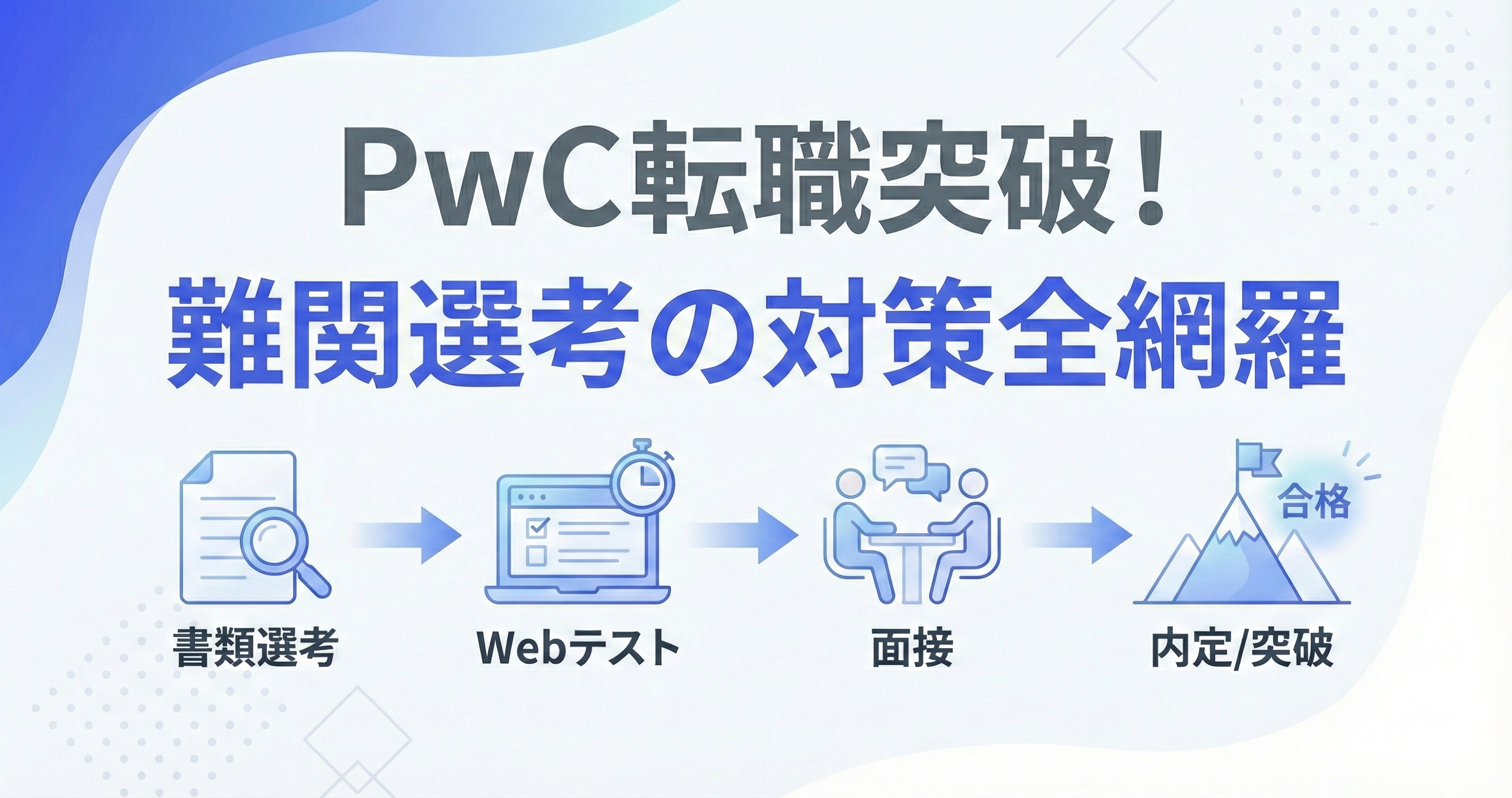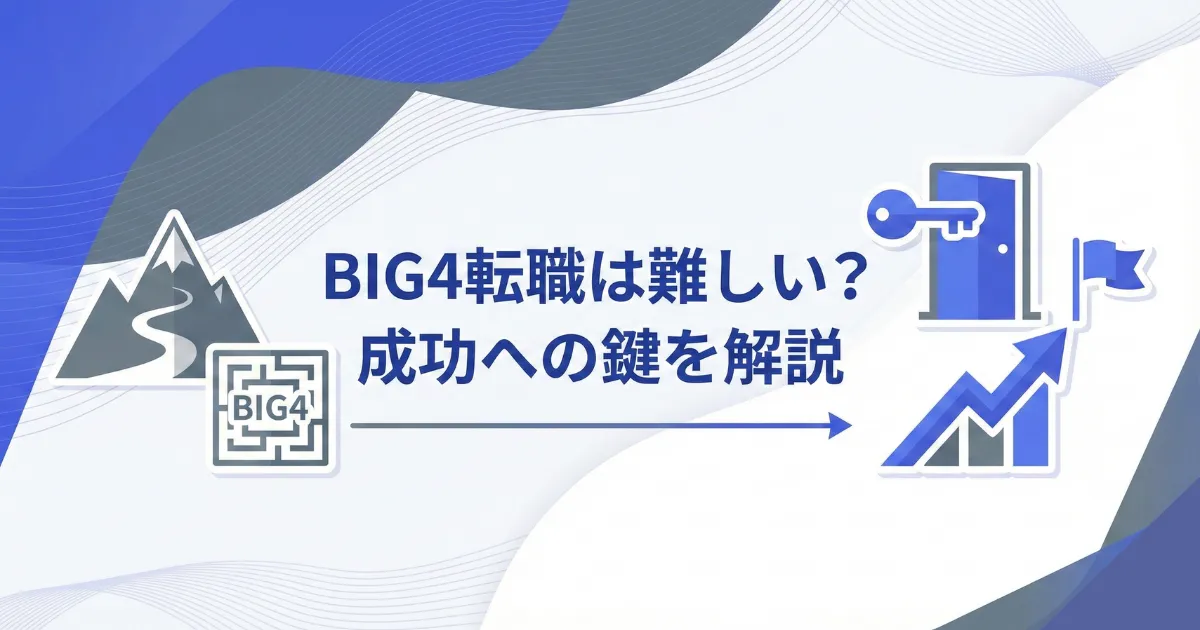2025/07/05 (更新日: 2026/02/04)
【テンプレあり】ESで通過する志望動機とは?|評価される志望理由とNG例も紹介
目次
📌 ESの志望動機、どう見られている?|選考通過者が押さえていたポイントとは
🔶採用担当は志望動機で何を見ているのか?
🔶「どこでも通用する志望動機」がNGな理由
🆗 通過する志望動機の共通点とは?|OK・NG例を徹底比較
🔶【OK例】「なぜその企業なのか」が明確な志望理由
🔶【NG例】抽象的で誰にでも当てはまる志望動機
📝 【テンプレ公開】誰でも書ける!ES志望動機の構成フォーマット
🔶4ステップで完成!志望理由テンプレート
📎テンプレートの使い方と注意点
📚 【例文付き】ES志望理由の成功パターン3選
🔶例文①:コンサル志望の学生(論理性重視)
例文②:メーカー志望の学生(ものづくり志向)
⚠️ ES志望動機でよくある失敗とその対策
🔶「熱意が伝わらない」と言われる志望動機の共通点
🔶一度書いたら読み直すべき「3つのチェックポイント」
🎯 まとめ|志望理由は“企業と自分の接点”を言語化することがカギ
📌 ESの志望動機、どう見られている?|選考通過者が押さえていたポイントとは
🔶採用担当は志望動機で何を見ているのか?
ESの志望動機で採用担当者が見ているのは、まず企業理解の深さです。数ある企業の中でなぜその会社を選んだのかを具体的に理解しているかどうかが重要で、事業内容や強み、企業理念への共感が伝わることが求められます。
次に、自分の経験やスキルが企業のどの部分で活かせるか、企業が求める人物像と自分が合致しているかを示すこともポイントです。また、入社後にどんなことをしたいのか、どのように成長したいのかというビジョンや意欲が明確で、会社の成長やミッションに積極的に関わりたい気持ちが伝わるかも重要視されます。
🎯さらに、志望動機はただ「好きだから」という理由にとどまらず、論理的で一貫性があり、簡潔でわかりやすい文章で誠実な印象を与えることが求められます。
🔶「どこでも通用する志望動機」がNGな理由
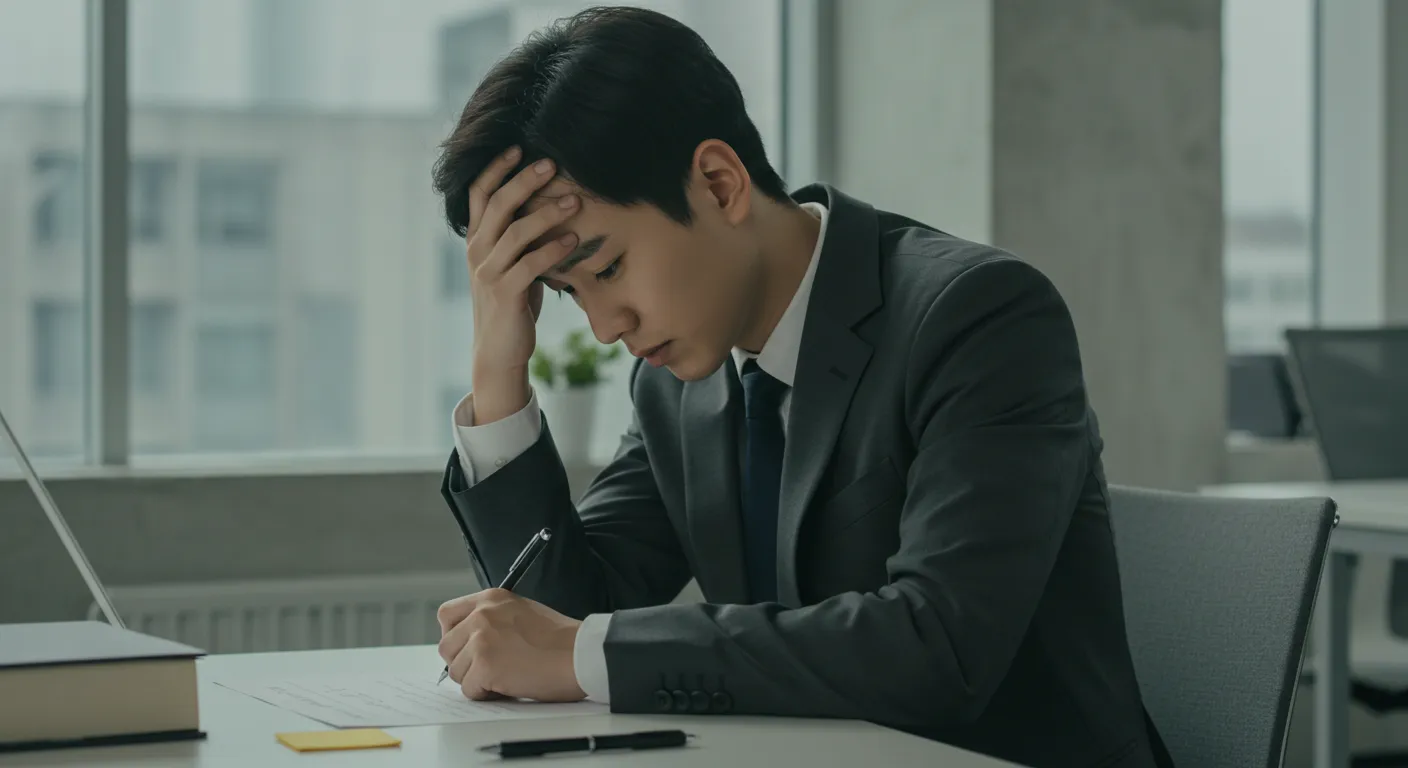
「どこでも通用する志望動機」がNGとされる理由は、採用担当者が志望動機から企業理解や応募者の本気度を見極めたいからです。
どの企業にも当てはまるような曖昧で一般的な志望動機は、応募者が企業独自の特徴や事業内容を深く理解していない、あるいは熱意や志望理由が薄いと受け取られやすくなります。そのため、企業に対して本気で向き合っている印象が弱く、「とりあえず応募しているだけ」「志望動機を使いまわしている」と判断されるリスクがあります。
⚠️また、どこでも使える志望動機は、自分の経験やスキルがその企業でどう活かせるか、入社後にどのように貢献したいかといった具体性や一貫性に欠けることが多く、論理的な説得力が不足します。
採用担当者は、応募者が自社で活躍するイメージを持てるかどうかを重要視しているため、抽象的で特徴のない志望動機ではその期待に応えられません。結果として、選考通過率が下がることになります。
🌟今すぐ実際の選考で出題されたケース面接の過去問を解いてみませんか?
CaseMatchは、『戦略コンサル内定者の3人に2人』が使っていた、ケース特化型AI面接練習サービスです。
✅ 完全無料・スマホでOK・24時間いつでも
✅ 1万件以上の回答データ×プロの評価から、あなたの回答を自動採点
✅また登録していると、コンサルや大手広告代理店などの【CaseMatch特別選考】にも挑戦できる!
👉今すぐケース面接の過去問を解いて、実力を測定してみませんか?
アクセンチュア過去問 - 耐久消費財の売上向上 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🆗 通過する志望動機の共通点とは?|OK・NG例を徹底比較
🔶【OK例】「なぜその企業なのか」が明確な志望理由
「私は金融業界の中でも特に○○銀行を志望しています。御行は国内最大規模の資産を誇るだけでなく、グローバルに展開するネットワークを活かして、多様な顧客ニーズに対応している点に強く魅力を感じています。大学時代にアメリカへ留学し国際経済を学び、異文化理解と金融知識を深める中で、御行のグローバル戦略やデジタル革新によるサービス拡充に貢献したいと考えるようになりました。御行はスマートフォンアプリ○○を通じたデジタル面での顧客体験の向上や、持続可能な社会への金融支援に取り組んでいる点に興味を惹かれました。入社後は、こうした先進的な取り組みの現場で、自分の知識やコミュニケーション力を活かし、顧客と社会に価値を提供していきたいです。
このような志望理由だと採用担当者に「この学生は本気で当社を志望している」「入社後の活躍イメージが湧く」と思わせることができ、選考通過につながりやすくなるでしょう。特に
- 企業の具体的な取り組みに触れている点
- 「なぜその企業か」が明確に説明されている点
- 自身の学び・関心とのつながりがある点
- 企業の社会的意義への共感が示されている点
- 入社後のビジョンが明確である点
- 論理的かつ一貫性のある構成である点
上記のようなポイントが特に評価されやすいESに共通しているといえるでしょう。
🔶【NG例】抽象的で誰にでも当てはまる志望動機
「私は人々の暮らしを支える金融業界に魅力を感じており、中でも御行は安定性と規模の大きさに強みがあると考え、志望いたしました。学生時代に培ったコミュニケーション力を活かして、多くの人々に貢献できる仕事がしたいと思っています。」
📌このような抽象的で誰にでも当てはまる志望理由では、採用担当者に「この学生は本気で当社を志望しているのだろうか」「他社でも同じようなことを言っているのではないか」と疑念を抱かせてしまい、選考通過が難しくなるリスクが大きくなります。
特に
- どの金融機関にも当てはまる内容である点
- 企業の具体的な取り組みに触れていない点
- 自分の経験との接点が弱い点
- 志望動機としての必然性がない点
上記のようなポイントはES落ちのリスクを高めてしまいます。
📝 【テンプレ公開】誰でも書ける!ES志望動機の構成フォーマット

🔶4ステップで完成!志望理由テンプレート
✅ ステップ①:業界を志望する理由
🚀まずは「なぜこの業界か」をしっかりと述べることで、あなた自身の志望の軸・価値観・問題意識を明確に伝えることができます。
このステップは、単なる憧れやイメージではなく、業界との接点や関心の根拠を示すパートです。ここが曖昧だと、「とりあえず金融」「なんとなく商社」といった印象を与えてしまい、説得力のある志望動機とはなりません。
🌟この部分で特に大切なのは、① 自分の経験・学び・問題意識と② 業界の社会的意義・役割を結び付けて話すことです。
この2つを結びつけることで、自分がその業界に「なぜ」惹かれたのか、どうしてその業界で働きたいと思ったのかが論理的かつ自然に伝わります。つまり、「業界の魅力」と「自分の背景」が接点を持ったとき、一貫性と納得感のある志望動機が生まれるのです。
✅ ステップ②:企業を選んだ理由(他社との差別化)
🔑ステップ①で「なぜこの業界か」が明確になったら、次は「なぜこの企業か」を示す必要があります。ここでは、数ある競合企業の中で、なぜ“その会社”を選んだのかという“企業選びの決定打”を示すことが求められます。
これは志望動機の中で最も差がつくポイントです。企業独自の特徴や価値観、取り組みにどれだけ具体的に触れているかで、本気度・企業研究の深さ・志望理由の説得力が一気に伝わります。
✅ ステップ③:自分の経験・強みとの接点|詳細解説
ここは、あなたがその企業にとって“どんな価値を提供できる人材か”を伝える最も重要なパートの一つです。
採用担当者は「この学生はうちで活躍できそうか?」という視点でESを読んでいます。
💬そのため、自分の強みや経験を「企業の仕事」「企業が求める人物像」とどう接続できるかを、具体的かつ論理的に示す必要があります。
具体的には書く上で意識すべきポイントは3つあります。
- ① 自分の経験を一つ選び、具体的に描写
- ② その経験から得た「強み」「学び」「スキル」を抽出
- ③ その強みが「企業のどんな仕事や価値観にフィットするか」を示す
「自分の過去」+「企業の未来」の接点を具体的に示せるかどうかで、ESの説得力が大きく変わります。企業が「この人、うちで活躍できそうだな」とイメージできれば、次の選考ステージにぐっと近づくでしょう。
✅ ステップ④:入社後に実現したいこと・貢献したいこと
💪志望動機の締めくくりにあたるこのステップでは、「この会社で何をしたいのか」「どのように貢献したいのか」を具体的に描くことが重要です。
採用担当者は、「この学生は、自分の将来をきちんとイメージしているか」「入社後にどのように会社に貢献してくれそうか」という観点で、ここを見ています。
志望動機の締めくくりとして大切なのが、「入社後に自分が何を実現したいのか、どのように会社に貢献したいのか」を明確に伝えることです。
これは単なる将来の希望ではなく、これまで述べてきた志望理由や自分の経験を踏まえたうえで、「それをこの会社でどう活かすか」という未来志向を示すパートでもあります。この視点を丁寧に描くことで、志望動機全体に一貫性のあるストーリーが生まれます。
逆に、ここを曖昧にしたまま終えてしまうと、「就職がゴール」「ただの受け身な姿勢」といった印象を与えてしまい、企業側に主体性や熱意が十分に伝わりません。「入社してからどんなことをしたいのか」「どのような価値を提供できるのか」を言語化できている学生は、将来の成長意欲が感じられ、入社後の定着率も高そうだというポジティブな評価につながります。
そのため、このパートでは「どんな分野で」「どんな価値を」「どう成長していきたいのか」といった点を、自分の言葉で具体的に描き出すことが重要です。これにより、企業にとって「この学生と一緒に働く未来」がリアルにイメージされやすくなり、選考通過の確度が高まります。
📎テンプレートの使い方と注意点
志望動機テンプレートは、何を書けばよいか迷っている人や、論理的につながった文章が作れないと悩んでいる人にとって非常に有効な思考ツールです。これは単なる“型”ではなく、自分の考えを整理し、「なぜこの業界か」「なぜこの企業か」「自分はどう活かせるか」「入社後何をしたいか」という4つの要素を、論理的につなげて説得力ある志望理由に仕上げるための設計図のようなものです。
要素を整理することで、自分の中にあるバラバラな情報を、ストーリーとして一貫性のある形に構築できます。さらに、各パートを「なぜ→だから」という因果関係でつなぐ意識を持つと、より説得力が増し、採用担当者にとっても読みやすく伝わりやすい文章になります。
ただし、テンプレートを使う上で注意すべき点もいくつかあります。まず、最も避けたいのが「型にはめただけ」の志望動機になってしまうことです。テンプレに沿っていても、中身が抽象的だったり、誰でも言えるような表現(例:「社会に貢献したい」「成長できる環境に惹かれた」)では、差別化にはなりません。必ず、自分自身の具体的な経験や思考を言葉にして、自分らしいエピソードで補強しましょう。
⏩加えて、すべての要素を無理に詰め込もうとすると、文字数制限に収まらず、内容が冗長になります。伝えたいことの優先順位をつけ、企業ごとに焦点を絞って簡潔にまとめることが大切でしょう。
📚 【例文付き】ES志望理由の成功パターン3選
🔶例文①:コンサル志望の学生(論理性重視)
私は、課題の本質を見抜き、構造的に解決策を導くことで社会に価値を提供できるコンサルティング業界に強く魅力を感じています。大学で経済学を学ぶ中で、単に「問題を解く」こと以上に、「問題を定義する力」が社会でいかに重要かを実感しました。特にゼミ活動で政策提言プロジェクトに参加した際、関係者の利害や制度的制約が複雑に絡む状況下で、課題の優先順位を見極めながら、実行可能な解決策を導き出すプロセスに強いやりがいを感じました。
中でも貴社を志望するのは、幅広い支援領域と、短期的なコスト削減提案にとどまらず、地域経済や人材構造の変化まで見据えた中長期の改革を設計されていた点に強く惹かれました。表面的な提案ではなく、「その企業が本当に変わるための仕組み作り」を支援できる点に、貴社ならではの価値を感じています。
入社後は、まずは業界知識やロジカルスキルをさらに磨きながら、1つ1つのプロジェクトに真摯に向き合いたいです。そして将来的には、「変化を起こすコンサルタント」として価値を発揮できる存在を目指したいと考えています。
上記の志望動機の良い点は以下になります。
① 「業界選択の理由」が明確で、思考の深さが伝わる
② 経験に裏付けされた志望動機になっている
③ 志望企業ならではの価値に言及している
これらの要素がそろっていることで、志望動機全体に一貫性と説得力が生まれており、「なぜコンサルなのか」「なぜこの会社なのか」「なぜ自分が適しているのか」という問いに対して、読み手が納得できる形で答えが提示されています。
その結果、企業側は応募者の志望度の高さだけでなく、入社後の活躍イメージや成長ポテンシャルを具体的に描きやすくなり、選考通過につながる内容に仕上がっています。
例文②:メーカー志望の学生(ものづくり志向)
私は、「目に見える形で人々の暮らしを支えるものづくり」に関わる仕事に強く惹かれ、メーカー業界を志望しています。大学では材料工学を専攻し、日常にある製品の背後にある高度な技術や緻密な設計思想を知る中で、モノを通じて社会に貢献することの奥深さに魅了されました。
中でも貴社を志望するのは、独自の技術力に裏打ちされた製品開発力と、グローバル市場での高い信頼に魅力を感じたからです。とりわけ、○○製品の〇〇分野への展開は、技術力だけでなく社会課題への応答力も感じさせ、単なる製造業にとどまらない社会的意義を持つと感じました。また、開発・製造・営業が密に連携しながら、現場の声を起点とした改良を積み重ねていく姿勢に、ユーザー起点のものづくりを重視してきた自分の志向と強い親和性を感じています。
入社後は、まずは製品開発の現場で現実の制約と真摯に向き合いながら、技術者としての基礎を磨きたいと考えています。そして将来的には、技術とユーザー視点を橋渡しできる人材として、社会に求められる製品づくりを牽引できる存在を目指します。
上記のような志望動機がいい点は以下のようになります。
① 業界選択の理由が明確で納得感がある
② 経験に裏打ちされたリアルな動機になっている
③構成が一貫しており、読みやすく説得力がある
⚠️ ES志望動機でよくある失敗とその対策
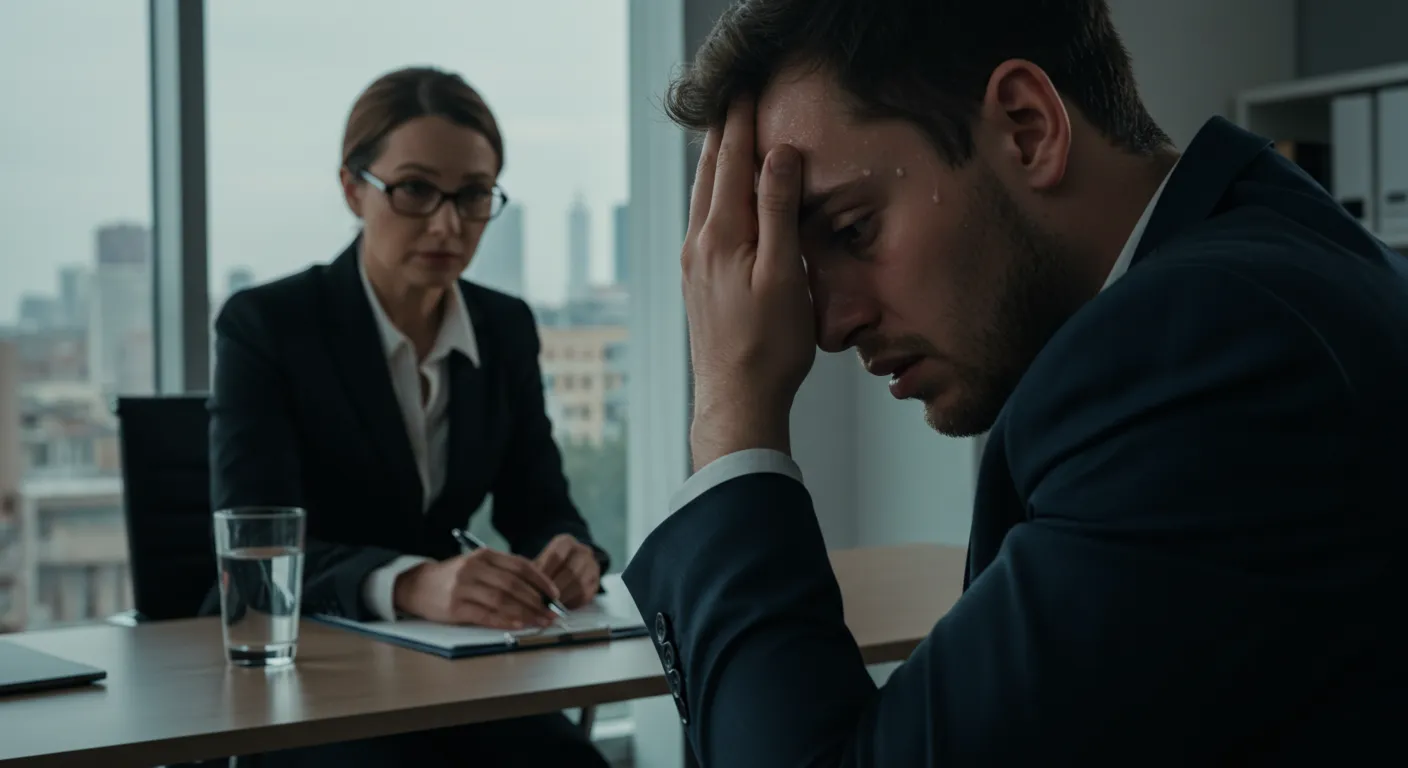
🔶「熱意が伝わらない」と言われる志望動機の共通点
ESの志望動機で「熱意が伝わらない」と言われる原因には、いくつかの共通点があります。まず多いのが、抽象的で誰にでも当てはまる内容になっているケースです。「社会に貢献したい」「成長できる環境に惹かれた」といった表現はよく見られますが、企業ごとの特徴や自分との接点が見えず、熱意は伝わりにくくなります。
🗂️また、自分の経験と企業の仕事とのつながりが弱い場合も、「なぜその会社なのか」が曖昧になります。
使っていた製品の話や有名企業だからといった理由だけでは、働く側としての視点が欠けてしまいます。
さらに、「やりたいこと」を並べるだけで、その背景にある動機や経験が語られていない場合、意欲の根拠が不明確になります。加えて、企業研究が浅く、どこでも通用するような内容になっていると、比較検討が甘く、志望度が低く見えてしまいます。
🔥また、入社後のビジョンが現実離れしていると、企業側は育成のイメージを持ちにくくなります。将来の夢を語るだけでなく、入社直後にどう行動し、どのように成長したいかを具体的に描くことが大切です。
つまり、「熱意がある志望動機」とは、自分の経験や価値観に根ざした必然性と、その企業ならではの魅力への共感が、論理的につながって語られていることです。テンプレではなく、自分の言葉で語ることが、採用担当の心を動かす第一歩です。
🔶一度書いたら読み直すべき「3つのチェックポイント」
✅ 1. 他社の名前に置き換えても成立していないか?
🔍このチェックは、「その企業でなければならない理由」が明確に伝わっているかを確認するためのものです。志望動機が本当に熱意あるものとして受け止められるには、企業ごとの特徴や価値観、ビジネスの進め方に対して、自分がどこに共感し、なぜ惹かれたのかを具体的に語れていることが不可欠です。
採用担当者は日々、数多くのエントリーシートに目を通しています。
🔍その中で、どの企業にも当てはまるような抽象的・汎用的な表現ばかりの志望動機は、「この学生はとりあえず出しているだけではないか」と疑念を持たれ、志望度が低く見られてしまう可能性が高くなります。
たとえば「社会に貢献したい」「成長できる環境に惹かれた」などは一見前向きな印象を与える言葉ですが、業界や企業を問わず通用してしまうため、差別化にはなりません。
🧱だからこそ、「この会社のどこに魅力を感じたのか」「なぜ他社ではなくここなのか」を深く掘り下げ、自分の経験や価値観と結びつけて語ることが重要です。
企業独自の取り組みや考え方を理解し、それに対する自分の考えや共感を乗せることで、はじめて“あなただからこその志望動機”になります。
✅ 2. 自分の経験と志望動機がつながっているか?
このチェックは、「なぜ自分がその志望に至ったのか」という思考の流れや背景に一貫性があるかを見直すためのものです。
🔍志望動機は、ただ“やりたいこと”や“目指す姿”を語ればよいわけではなく、その考えに至った理由や根拠となる経験・価値観がセットで語られている必要があります。
採用担当者が見ているのは、「この学生の志望動機には再現性や信頼性があるか」という点です。つまり、「ただの憧れ」や「なんとなく」ではなく、過去の経験から導かれた自然な思考の流れがあるかが問われています。
✅ 3. 入社後の姿がイメージできる内容か?
このチェックは、採用担当者が「この学生が入社後にどのように成長・活躍しそうか」を具体的にイメージできるかどうかを確認するものです。
🔍どんなに素晴らしい経験や熱意を語っていても、「入社後にどう行動し、何を学び、どのように貢献したいのか」が描かれていなければ、“未来の再現性”が感じられず、評価を下げてしまう可能性があります。
企業は「ポテンシャル採用」とはいえ、できるだけリアルに入社後の姿を想像できる人材を選びたいと考えています。自社の育成方針やキャリアステップに対して、志望者が理解と準備を持っているかは、重要な評価ポイントです。
🎯 まとめ|志望理由は“企業と自分の接点”を言語化することがカギ
🔥エントリーシートの志望動機で最も大切なのは、「その企業と自分がなぜフィットするのか」を、経験や価値観をもとに“自分の言葉”で言語化することです。
採用担当者は、「この学生はうちで本当に活躍できそうか」「他の企業ではなく、なぜうちを選んだのか」を見極めようとしています。だからこそ、単に「やりたいこと」や「憧れ」だけでなく、これまでの経験で何を感じ、どんな気づきを得て、その企業を志すようになったのかという“ストーリー”が必要です。
そのためには、
- 企業独自の魅力を丁寧にリサーチすること
- 自分の体験や価値観と照らし合わせること
- そこに生まれる「接点」や「共感」を、筋道を立てて表現すること
が不可欠です。
🧭「企業について調べた情報」+「自分のリアルな体験」=“あなたにしか書けない志望動機”になります。
誰にでも当てはまるような一般論ではなく、「私はなぜこの会社に入りたいのか」を論理と感情の両面から語れるかどうかが、選考突破のカギなのです。