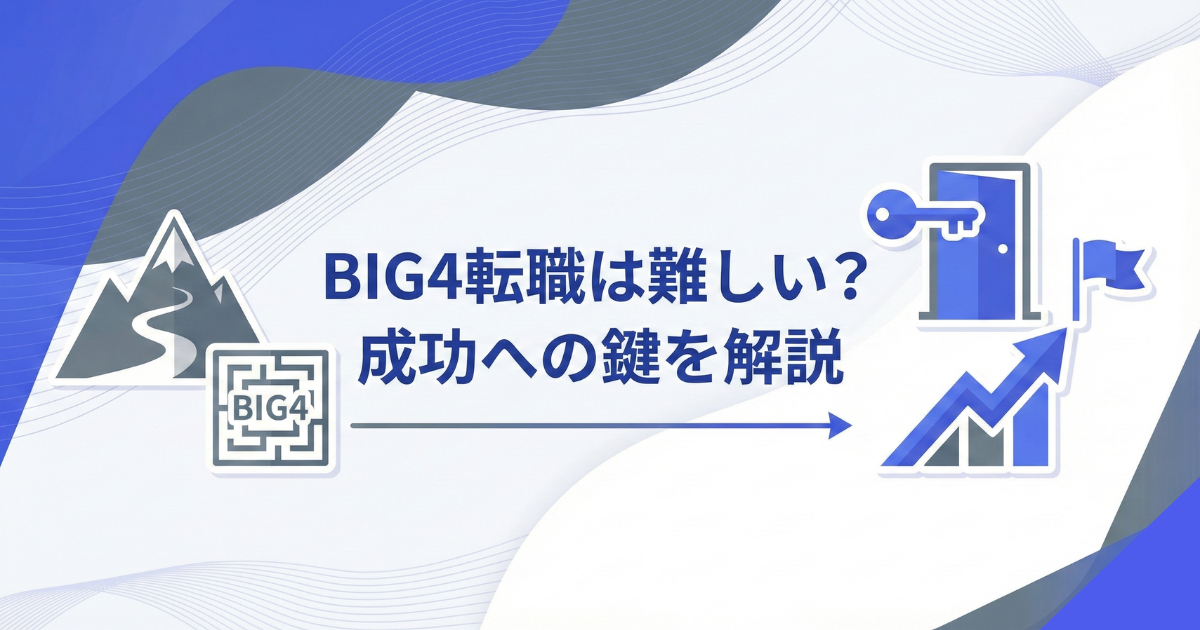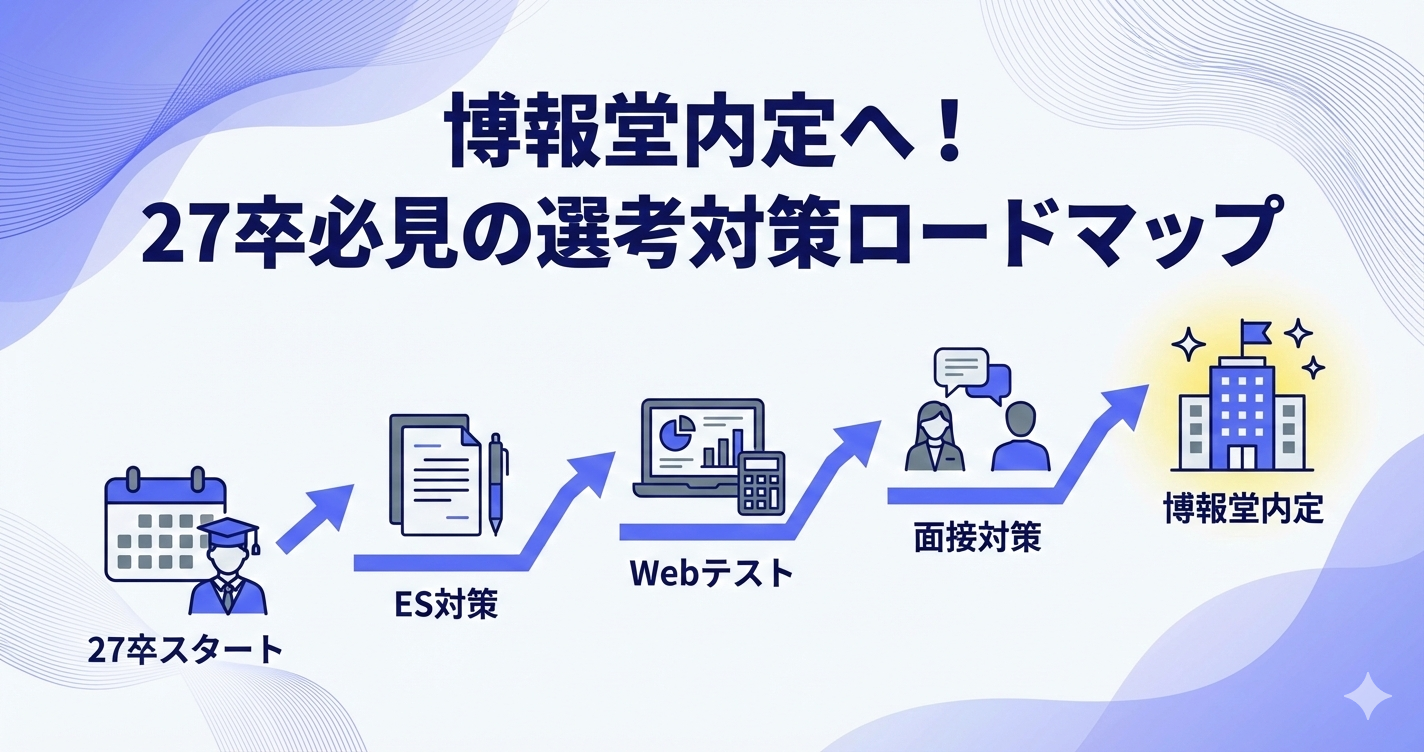2025/08/07 (更新日: 2025/12/01)
【初心者向け】3C分析をわかりやすく解説|マクドナルド・スタバの事例で学ぶフレームワーク活用法
目次
🧩 そもそも3C分析とは?|マーケティング戦略の基本フレームワーク
🔶3C=Customer・Company・Competitor の意味とは?
🔶3C分析の目的と活用される場面
🔶3C分析のメリット・限界
🪜 3C分析のやり方|順番と進め方をわかりやすく解説
🔶① Customer(市場・顧客)をどう分析する?
🔶② Company(自社)分析で見るべきポイントとは?
🔶③ Competitor(競合)を比較分析するコツ
🍔 【事例1】マクドナルドの3C分析|成長を支えた戦略とは?
🔶Customer:顧客ニーズの変化と対応
🔶Company:店舗運営とマーケティング戦略
🔶Competitor:競合との差別化ポイント
☕【事例2】スターバックスの3C分析|ブランドが愛され続ける理由
🔶Customer:ターゲット顧客の深堀り
🔶Company:体験価値を重視した店舗設計
🔶Competitor:競合カフェとの違い
🔄 他のフレームワークとの違いは?|SWOT・4Pとどう使い分ける?
🔶SWOT分析との使い分け方
🔶4P(マーケティングミックス)との関係性
🔶実務での組み合わせ例と考え方
🛠️ 3C分析を実践で使うには?|おすすめの練習法と注意点
🔶身近な企業で3C分析をしてみよう
🔶就活・面接・レポートで使える3C分析のコツ
🔶よくあるミスと注意点
おわりに
🧩 そもそも3C分析とは?|マーケティング戦略の基本フレームワーク

マーケティングにおける最重要フレームワークのひとつが「3C分析」です。市場で勝ち抜くための戦略を立てるうえで、自社だけでなく、顧客(Customer)・自社(Company)・競合(Competitor)という3つの視点から環境を把握することが不可欠です。企業の経営戦略から商品開発、広告戦略に至るまで、あらゆる意思決定の基礎となるフレームワークとして幅広く使われています。
🔶3C=Customer・Company・Competitor の意味とは?
3C分析は、以下の3つのC(要素)を切り口に、ビジネス環境を構造的に整理する手法です。
- Customer(顧客・市場)
誰に価値を提供するのか?市場規模や成長性、顧客ニーズ、消費者行動、ターゲット層の変化などを分析します。
例:20代女性の間でノンカフェイン飲料が流行っているとしたら、それは大きな市場機会です。 - Company(自社)
自社の強みや弱み、資源、ブランド力、技術力などを客観的に評価します。自社がどんな価値を提供できるのか、どんな領域で優位性があるのかを確認します。
例:製造コストを抑える独自技術や、地域密着のブランド力などが挙げられます。 - Competitor(競合)
同じ市場で戦うライバル企業の動向や戦略を分析します。競合の強み・弱み、シェア、ポジショニング、ターゲットなどを明らかにし、差別化の可能性を探ります。
例:価格競争が激化している市場で、あえてプレミアム戦略を取ることで競合と一線を画すなど。
🌟この3つの視点を組み合わせることで、単なる「自社視点の戦略」ではなく、外部環境との整合性を持った実効性の高い戦略が導き出せるのです。
▼その他にケース面接で活用できるフレームワークはこちらから
ケース面接の必須フレームワーク一覧|効果的な使い方と合格するコツを解説 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🔶3C分析の目的と活用される場面
3C分析の主な目的は、「顧客にとって魅力的であり、自社の強みを活かし、競合に勝てるポジショニングを見つけること」です。
活用される場面は非常に広く、以下のようなケースで使われます。
- 新規事業・サービスの企画
- 商品のリブランディング
- 広告・マーケティング施策の立案
- 中長期的な経営戦略の策定
- コンサルティングやビジネスコンテストでの環境分析 など
たとえば新商品を開発する際、「ターゲット顧客が求める価値は何か?」「自社の技術でそれを実現できるか?」「競合との差別化は可能か?」といった問いに答えることで、より戦略的な意思決定が可能になります。
▼3C分析を使った実際のケース面接の解き方については以下にて解説中
ケース面接の解き方を徹底解説|過去問を通して学ぶ“内定レベル”の思考vol1 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🔶3C分析のメリット・限界
■ メリット
- 構造的な思考ができる
複雑なビジネス環境を「顧客・自社・競合」の3軸に分けて整理することで、視野が広がり、思考の抜け漏れを防げます。 - 具体的なアクションにつながる
自社の立ち位置や競争優位性が明確になるため、次の一手が考えやすくなります。仮説→分析→戦略立案の流れがスムーズになります。 - 多くのフレームワークと組み合わせやすい
SWOTや4P分析など、他の分析ツールとも相性がよく、戦略設計の起点として汎用性が高いのも特徴です。
■ 限界
- 情報の質に左右される
3C分析は「考える型」ではあるものの、元となる情報が浅かったり誤っていたりすると、分析結果も正確性を欠きます。とくに顧客ニーズや競合の強みなどは、客観的なデータに基づいた調査が不可欠です。 - 「どう戦うか」は別途設計が必要
3Cは「現状把握」や「機会と課題の発見」には強いですが、「戦略の具体化」には限界があります。3C分析を踏まえたうえで、ポジショニング戦略や4P戦略などへとつなげていく必要があります。
🌟今すぐ実際の選考で出題されたケース面接の過去問を解いてみませんか?
CaseMatchは、『戦略コンサル内定者の3人に2人』が使っていた、ケース特化型AI面接練習サービスです。
✅ 完全無料・スマホでOK・24時間いつでも
✅ 1万件以上の回答データ×プロの評価から、あなたの回答を自動採点
✅また登録していると、コンサルや大手広告代理店などの【CaseMatch特別選考】にも挑戦できる!
👉今すぐケース面接の過去問を解いて、実力を測定してみませんか?

🪜 3C分析のやり方|順番と進め方をわかりやすく解説

🔶① Customer(市場・顧客)をどう分析する?
まず最初に行うべきは、「Customer(顧客・市場)」の分析です。なぜなら、どんなに優れた製品やサービスを持っていても、ニーズのない市場では売れないからです。
■ 見るべきポイント:
- 市場規模と成長性:どれくらいの市場か?今後伸びそうか?
- 顧客セグメント:性別・年齢・ライフスタイル・価値観など
- ニーズと課題:顧客は何に困っていて、どんな価値を求めているか?
- 購買行動:何をきっかけに買うのか?比較検討はするのか?
■ 具体例:
たとえば健康志向が高まる中で、「低糖質」「プロテイン入り」「グルテンフリー」といったキーワードが注目されている場合、これらのニーズを満たす商品開発は大きな機会となります。
■ 情報収集の手段:
- 公式統計データ(経済産業省、総務省など)
- 市場調査会社のレポート(矢野経済研究所など)
- SNSやレビューサイト、アンケート結果
🔶② Company(自社)分析で見るべきポイントとは?
顧客や市場のニーズを把握したら、次は「自社には何ができるか」を見極めます。ここでは自社の強み・弱みを客観的に把握し、それが市場でどう活かせるかを検討します。
■ 見るべきポイント:
- 経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報):技術力や人材、財務体質
- ブランド力や信頼性:業界内での評判、顧客からの認知度
- 過去の成功事例やノウハウ:成功・失敗から得られた学び
- 現在のポジション:ターゲット市場でどのように見られているか?
■ 具体例:
高品質な製品を安定供給できる製造ラインを持っている場合、「大量生産・低コスト化」が競争力の源泉になり得ます。一方で、小回りの利くベンチャーなら、迅速な企画・試作が強みになるかもしれません。
■ 自社分析の方法:
- 社内ヒアリング
- KPIや過去の財務データ
- SWOT分析との併用も効果的
🔶③ Competitor(競合)を比較分析するコツ
最後に分析すべきは、競合他社の動向やポジショニングです。市場で成功するには、「自社にできて競合にできないこと」「競合が提供できない価値」を見つけ、差別化することがカギになります。
■ 見るべきポイント:
- 主な競合企業とそのシェア:業界の主要プレイヤーを特定
- 競合の強み・弱み:価格戦略、販路、技術、ブランド力など
- ターゲット層や訴求ポイント:どの層に、何を強みに売っているか
- 戦略の変化:新規参入・撤退・提携などの動きもチェック
■ 具体例:
あるコーヒーチェーンが「安さ」で勝負している場合、価格競争に巻き込まれず「空間体験」や「地域限定メニュー」で差別化する戦略が考えられます。
■ 情報収集の方法:
- 競合のWebサイト・IR情報・プレスリリース
- 店舗観察(フィールドワーク)
- 顧客レビューやSNSでの評判
【補足】3C分析の“正しい順番”と理由とは?
3C分析では、Customer → Competitor → Companyの順で進めるのが基本とされています。
なぜこの順番が推奨されるのかというと、「まず市場とニーズを把握したうえで、自社と競合の立ち位置を比較・調整する」という考え方が戦略設計において自然だからです。
たとえば最初にCompany(自社)だけを分析しても、「そもそもその強みが市場で求められているか?」「競合も同じようなことをしていないか?」という視点が抜け落ちてしまいがちです。
🍔 【事例1】マクドナルドの3C分析|成長を支えた戦略とは?

🔶Customer:顧客ニーズの変化と対応
マクドナルドのターゲットは極めて広範です。たとえば、以下のような複数の層を同時に捉える戦略をとっています。
- 若年層・学生:お小遣いやバイト代で手軽に食事を楽しみたい。シェイクやポテトをシェアして友人と過ごす場としても機能。
- ビジネスパーソン:ランチや夕食をサッと済ませたい、移動中や外回りの合間にコーヒーを一杯飲みたい。
- ファミリー層:子ども向けの「ハッピーセット」や、親子で気兼ねなく過ごせる空間が求められる。
- 高齢層やシニア客:早朝や昼下がりに静かな場所で一息つきたいニーズに応えるメニュー・空間設計。
こうした多様なニーズに応えるために、マクドナルドは商品ラインアップだけでなく「時間帯別メニュー」「モバイルオーダー」「デリバリー対応」など、サービス設計全体を顧客視点で最適化しています。
近年は、健康志向の高まりや食の安全性への関心に応えるべく、サラダ・低カロリー商品・アレルゲン表記の徹底なども強化。単なる“ファスト”だけではなく、「選べる・安心・満足感」までを網羅するブランドとして顧客との関係を深めています。
🔶Company:店舗運営とマーケティング戦略
🌟マクドナルドの強みは、「チェーンオペレーションの極致」とも言えるほどの仕組み化・標準化の徹底にあります。
これにより、どの国・地域・時間帯でも「いつものマック」が味わえるという、安定的な顧客体験を提供しています。
■ 主な自社の強み:
- オペレーションの自動化・分業化:厨房の動線、調理手順、接客の流れまでが分刻みで設計されており、誰でも一定レベルのサービス提供が可能。
- スケールメリットを活かした調達・物流:全世界で同一規格の食材を大量に仕入れることでコストを最小限に抑える。冷凍・冷蔵のサプライチェーンも高精度。
- ブランドマーケティングの巧みさ:全国テレビCMやSNSキャンペーン、季節・映画とのコラボ施策などで継続的に話題を生み、リピーターを獲得。
- デジタル化への対応:公式アプリのクーポンやモバイルオーダー、キャッシュレス決済の導入により、顧客接点を拡張。
さらに、近年では「居心地の良さ」や「体験価値」にも注力しています。木目調のインテリアやカフェ風の店舗デザイン、充電設備やWi-Fiの整備など、単なる“食事をする場”から“過ごす場”へと進化を遂げています。
📝このように、自社のリソース(資産・人材・仕組み)を最大限活かしながら、環境変化に柔軟に適応できるのがマクドナルドの強さの根幹です。
🔶Competitor:競合との差別化ポイント
マクドナルドの競合は、同業のハンバーガーチェーンにとどまりません。以下のように、“手軽に食事ができる”という観点での競合が広がっているのが近年の特徴です。
- 直接競合:モスバーガー、ロッテリア、バーガーキング、フレッシュネスバーガーなど。同様のメニューを展開し、価格や品質、オリジナリティで差別化を図っている。
- 間接競合:コンビニ(おにぎり・ホットスナック)、牛丼チェーン、ファミレス、カフェチェーンなど。特に、テイクアウト・デリバリー分野ではコンビニとの競争が激化。
これに対してマクドナルドは、「徹底した効率性・立地戦略・ブランド力」で差別化を図っています。
- 駅前・商業施設・幹線道路沿いなど、全国3,000超の強力な店舗網
- 期間限定メニューやご当地商品で飽きさせない商品開発
- 家族向け・高齢者向け・若者向けなど、多層へのアプローチ
- 「夜マック」「倍バーガー」など、時間帯ニーズに対応した販売施策
さらに、広告での差別化も抜かりありません。たとえば、社会的課題に寄り添ったメッセージ広告、感情に訴えるストーリーテリング型CMなどで「単なるチェーン店」から「共感されるブランド」への転換を進めています。
☕【事例2】スターバックスの3C分析|ブランドが愛され続ける理由

🔶Customer:ターゲット顧客の深堀り
スターバックスの顧客層は、単なる「コーヒーを飲みたい人」ではなく、ライフスタイル・体験・共感価値を求める層です。
- トレンド志向の若年層や女性層:SNS映えする限定メニューやカスタマイズを好み、スタイリッシュな空間で過ごしたい。
- ビジネスパーソン:静かで快適な空間で仕事やミーティングをしたい、ながら飲みにも適した店舗を重視。
- ライフスタイル重視層:時間をかけて「過ごす」場所として、香り・インテリア・BGM・接客などの五感体験を求める顧客。
最近では、健康志向や機能性飲料を求める動きに対応し、「プロテインインフューズドコールドフォームドリンク」「低糖ラテ」なども導入しています。こうした商品やサービスは、顧客の多様なニーズを鋭く捉え、深い共感を得られるブランド体験につながっています。
🌟また、「ゆったり過ごす」体験価値を最大化することで、顧客はスターバックスを日常生活の一部として捉えるようになり、単なる飲料提供の場を超えた「第三の場所」として選ばれ続けています 。
🔶Company:体験価値を重視した店舗設計
スターバックスの自社の強みは、「体験を設計する力」と「ブランド文化の一貫性」にあります。
- “Third Place” を体現する店舗設計:木目調のインテリア、BGMの選定、季節ごとの装飾など、居心地のよさと個性を融合。
- カスタマイズ性と高品質のコーヒー:ミルクの種類、シロップ、トッピングなどを自由に選ぶことができる柔軟なオーダー体験。
- デジタルとリアルを融合した顧客接点:公式アプリによる事前注文・ポイント管理・モバイルペイメントシステムの導入。
- ブランドストーリーとCSR活動:フェアトレードコーヒー、地域社会支援、環境配慮型店舗運営が企業理念と一体化。
🌟CEO Brian Niccol の下で展開される「Back to Starbucks」戦略では、アプリ限定や無人店舗に偏らず、人と空間の温かみを取り戻す方向へ舵を切っています。具体的には、モバイル注文専用店舗の閉鎖、座席やドライブスルーを伴う新フォーマット店舗、500 MUSD超のスタッフ教育投資などが進行中です 。
さらに、メニューの簡素化(約30%縮小)や約4分以内の注文完了という待ち時間短縮への取り組みも、顧客体験の改善に直結しています 。
🔶Competitor:競合カフェとの違い
スターバックスが競合と一線を画すのは、単なる商品競争や価格競争ではなく、「体験価値」と「ブランド文化」で勝負している点です。
- 直接競合:ドトール(日本)、タリーズ、ダンキンドーナツ、Tim Hortons、McDonald’s の McCafé など。低価格戦略や貢献型メニューで顧客を奪い合います 。
- 間接競合:コンビニコーヒー、ファミレス、地元カフェなど。早さや手軽さを求める顧客にとっては強力な代替選択肢。
さらに、技術主導の新興勢力として、中国発の Luckin Coffee が注目されます。Luckin はアプリベースで$2~3の低価格コーヒーを提供し、急速なグローバル展開を進めています。最近ではニューヨークにも進出し、スピードと価格でスターバックスと真っ向勝負を繰り広げています 。
🌟これに対し、スターバックスは「温かみ」「接客」「居心地」優先型の戦略で差別化を維持しています。
例えば、カスタム注文を重視する「Green Apron Service」モデル、セルフ・コンディメントバーの復活、店舗スタッフの拡充・訓練など、利便性と体験の両立に注力しています 。
🔄 他のフレームワークとの違いは?|SWOT・4Pとどう使い分ける?
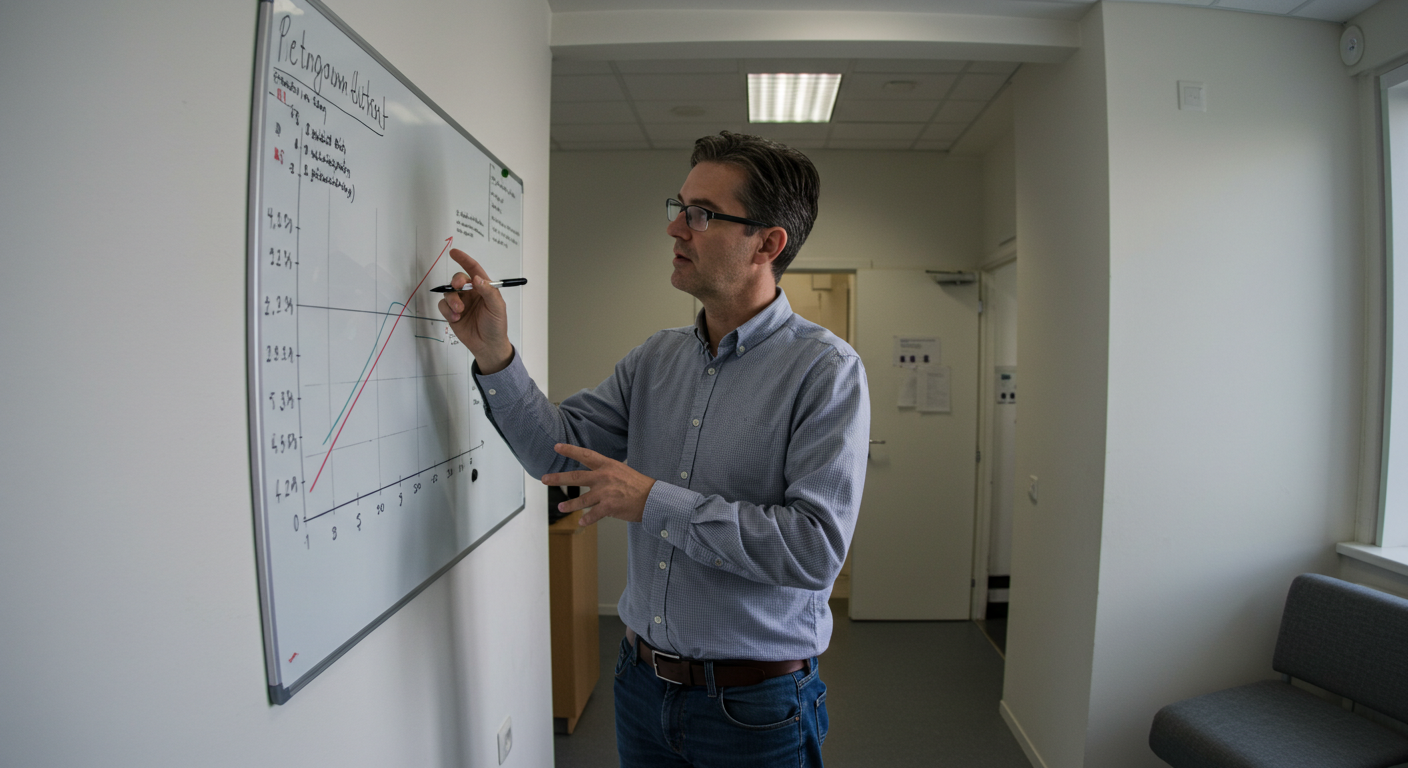
🔶SWOT分析との使い分け方
■ 3Cは「外部環境の整理」、SWOTは「戦略判断の枠組み」
3C分析は「顧客・自社・競合」の3つの視点から市場を構造的に把握するためのフレームワークです。
一方、SWOT分析は、内部環境(Strength/Weakness)と外部環境(Opportunity/Threat)に分類して、「どの強みを活かし、どんな機会を狙うか」「どんなリスクに備えるか」を考えるためのフレームです。
■ 3Cで情報を集め、SWOTで「判断軸」に落とし込む
たとえば食品メーカーが新商品を企画する場合、まず3Cで「顧客ニーズの変化」「競合の価格帯や品質」「自社の製造・流通体制」などを整理します。その上で、
- Strength(高品質な原材料調達)
- Weakness(ブランド認知が低い)
- Opportunity(健康志向の高まり)
- Threat(大手企業の広告攻勢)
のように要素を抽出し、戦略的にどこを強化すべきかを判断する、という使い方になります。
■ ケース面接やレポートでも「3C→SWOT」の順が鉄則
就活でも、まず3Cで抜け漏れなく情報を集めたうえで、SWOTでシンプルに要点をまとめる、というフローが論理性・構造性のある回答につながります。
🔶4P(マーケティングミックス)との関係性
■ 3Cは「戦略の方向性」、4Pは「戦術の設計図」
3C分析は、誰に・何を・どうやって勝つかの方向性を定めるものです。
🌟一方、4Pは「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」という4つの観点で、実際の打ち手を具体的に設計するためのフレームです。
■ 3Cで“何を売るか”を考え、4Pで“どう売るか”を決める
たとえば新しい化粧品ブランドを立ち上げる場合、
- 3C分析:Z世代女性が主なターゲット/競合は韓国系ブランド/自社の強みは安全性と価格
- 4P分析:
- Product:無添加・ビーガン処方
- Price:手頃な1,500円台
- Place:バラエティショップやEC中心に展開
- Promotion:TikTokでの体験型動画+クーポン配布
🌟このように、3Cで環境を理解し、4Pで具体策を形にするのが、最も実践的な流れです。
🔶実務での組み合わせ例と考え方
■ フレームワークは「役割分担」で考える
3C・SWOT・4Pは対立するものではなく、それぞれ異なる役割を担っています。複数を段階的に組み合わせることで、戦略の構造と説得力が大きく向上します。
■ 具体的な活用ステップ(飲食業界の場合)
- 3C分析:市場ニーズ、競合店舗、自社のオペレーション力を把握
- SWOT分析:強み(立地の良さ)×機会(テイクアウト需要)を掛け合わせて戦略の柱を定める
- 4P分析:
- Product:テイクアウトに特化したワンハンドフード
- Price:昼はワンコイン/夜はセットメニュー強化
- Place:駅ナカ・商業施設を中心に出店
- Promotion:LINEクーポンとSNSで集客強化
■ 就活の面接やレポートでも使い分けを意識
ES・プレゼン・選考課題などでは、「3Cで課題を発見し、SWOTで要素整理、4Pでアイデアを形にする」という三段構えが非常に有効です。構造的な思考力を伝えるフレームワーク活用の王道として押さえておきましょう。
🛠️ 3C分析を実践で使うには?|おすすめの練習法と注意点

3C分析を「理解する」だけでは意味がありません。実際に使いこなすには、手を動かして何度も分析を繰り返し、仮説思考や構造的な視点を磨くことが必要です。この章では、3C分析を身につけるための練習方法や、就活・面接での活用法、そして陥りがちなミスとその対策を紹介します。
🔶身近な企業で3C分析をしてみよう
■ 最初は「知っている企業×3C」で感覚をつかむ
はじめから複雑な業界に挑戦する必要はありません。まずは「自分が日常的に接している企業」からスタートするのがベストです。
たとえば:
- マクドナルド(ファストフード)
- ユニクロ(アパレル)
- スターバックス(カフェ)
- 無印良品(生活雑貨)
- 任天堂(ゲーム)など
これらは3Cそれぞれの視点で特徴が分かりやすく、初学者にも分析しやすい企業です。
■ 実地観察とデスクリサーチを組み合わせよう
3C分析の質を高めるには、「見たこと・使ったこと」+「調べたこと」を掛け合わせるのが効果的です。
- Customer(顧客):SNS、口コミサイト、レビュー、ターゲット層の特徴
- Company(自社):企業HP、IR資料、店頭観察、店員との会話
- Competitor(競合):競合他社のサービス比較、料金体系、ポジショニング
■ 分析内容は「表形式」または「スライド形式」でまとめる
練習時は、A4用紙やGoogleスライドで「3Cごとに枠を作る」と視覚的に整理しやすく、思考の抜け漏れを防げます。実務やプレゼンでもそのまま使えるフォーマットに慣れておくのがオススメです。
■ 上級者は「時系列」や「地域別」分析にも挑戦
より深く練習したい場合は、時期や地域による違いも意識してみましょう。
例:スターバックスの地方 vs 都市型店舗での競合・顧客の違い/2020年のコロナ禍 vs 2024年の回復期でのニーズ変化
🔶就活・面接・レポートで使える3C分析のコツ

■ ケース面接では「構造立ての基準」として使う
コンサルや広告代理店などのケース面接では、回答の正確さよりも「考え方の筋道」が評価されます。
🌟そこで、「まず3Cの3軸で整理しよう」という意識を持つだけで、ロジックに説得力が出ます。
例:
「売上が落ちている原因は何か?」という問いに対して…
- Customer:顧客層の離反/ニーズの変化
- Company:商品力低下/プロモーション不足
- Competitor:新興勢力の参入/他社の価格戦略
このように整理したうえで、最も重大な原因を特定し、対策を提案する流れが理想です。
■ レポートやビジネスコンテストでも使える汎用フレーム
3C分析は、企業研究だけでなく、業界分析や社会課題に関するレポートにも応用可能です。特にビジネスコンテストやインターン選考では、3C→SWOT→4Pのような連携使用が非常に効果的です。
🔶よくあるミスと注意点
■ Company分析だけに偏るのはNG
多くの人が「その企業について知っていること=分析」だと思いがちですが、それは3Cの一部にすぎません。「自社を客観的に見る」「市場の変化を見る」という視点を忘れないようにしましょう。
■ Customer=ユーザーだと単純化しすぎない
Customerには、「購入者」「意思決定者」「利用者」「影響者」など複数の立場があります。
たとえば、教育業界では:
- 子ども(利用者)
- 保護者(購入者)
- 教育委員会(意思決定者)
このようにステークホルダーを複層的に捉えることで、より実践的な分析になります。
■ 「競合がわからない…」は代替手段の発想で突破
競合が思いつかないときは、「同じニーズを満たす別の手段は何か?」を考えてみてください。
- スターバックスの競合→他のカフェチェーンだけでなく、コンビニコーヒーや在宅用ドリップ商品も含まれる
- メルカリの競合 → ラクマ、ヤフオクだけでなく、リユースショップやLINEフリマも競合になりうる
おわりに
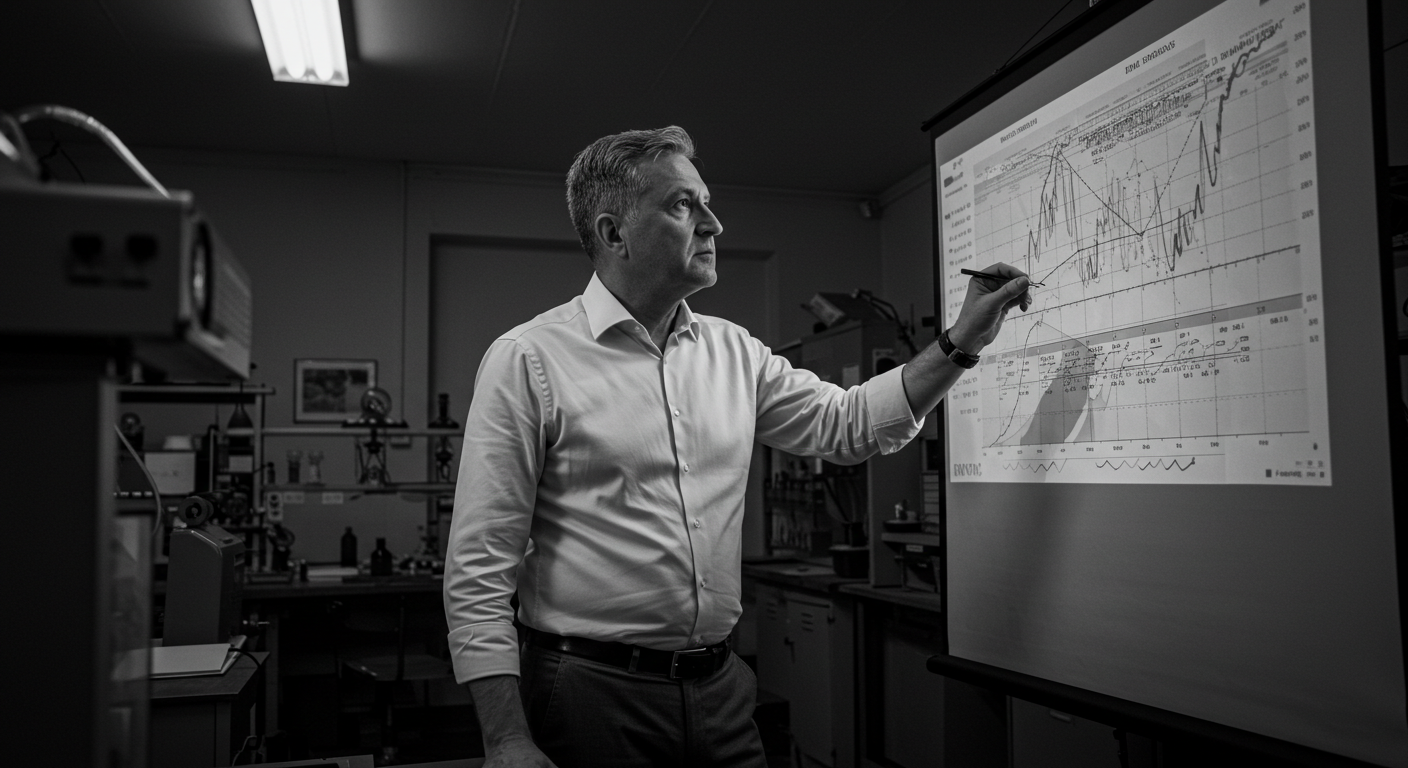
3C分析は、顧客・自社・競合をバランスよく捉えることで、戦略の“抜け”や“偏り”を防ぐことができる強力なフレームワークです。他の分析手法と組み合わせることで、思考の深さと実行力が格段に向上します。まずは身近な企業から始め、ケースやレポートで何度も使ってみることが習得の近道です。「3Cで整理→SWOTで要点化→4Pで具体策へ」という型を意識すると、説得力のあるアウトプットが可能になります。“使える分析力”を身につける第一歩として、3C分析は必ず押さえておきたい基本です。