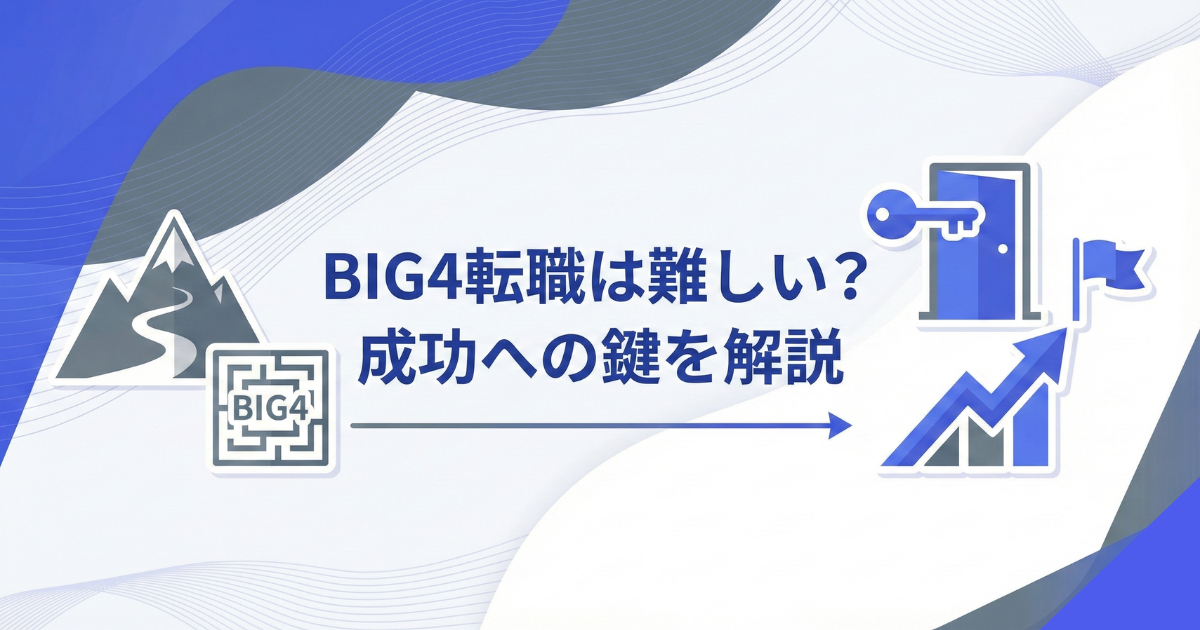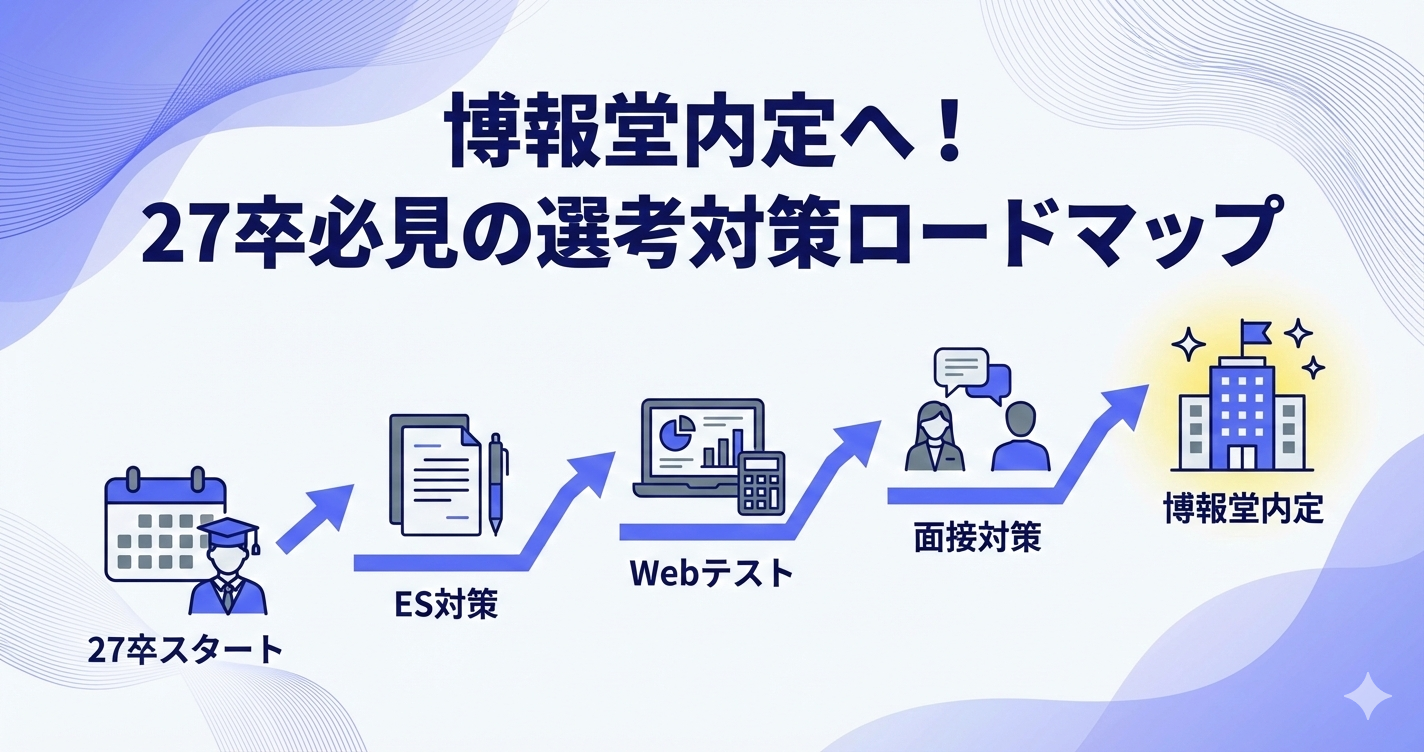2025/07/02 (更新日: 2025/12/08)
【2025年版】最新ケース面接例題まとめ|解き方まで徹底解説
目次
🧠 ケース面接とは?押さえておきたい基本知識
🔶ケース面接の目的とは?企業が見ている3つの視点
🔶どの業界で出る?ビジネス・IT・公共系の出題傾向の違い
🔶ケース面接と通常面接の違いとは?
📌 【例題で学ぶ】ビジネス系ケース面接の思考プロセス
🔶例題:国内で人気のカフェチェーンが東南アジア市場に進出する戦略を立てよ
🔶例題:中規模テーマパークの売上向上
🔶ビジネス系ケースの例題8選
🔶コンサルティングファームが求める「ロジカルさ」とは
🏛 【例題で学ぶ】公共系ケース面接の難しさとは?
🔶例題:サッカーチームのケガ問題をどう解決する?
🔶例題:迷子をどう減らすか?
🔶公共系ケースの例題3選
🔶公共系で問われる「多様なステークホルダー視点」
🧩例題を通して分かった“通過できる人”の共通点
🔶「正解を出す」より「仮説を立てる」姿勢がカギ
🔶話し方・構成力・柔軟性の3点が差を分ける
📝 ケース面接に受かる人がやっている練習法
🔶ノー勉はNG?効果的な練習ステップと頻出テーマ
🔶通過者が使っていたおすすめ問題集・書籍
🔶模擬練習のやり方とフィードバックの受け方
🏁 まとめ|本番で力を発揮するために準備すべきこと
🧠 ケース面接とは?押さえておきたい基本知識

ケース面接とは、与えられたビジネス課題に対して、制限時間内に論理的な仮説・解決策を導くことを求められる面接形式です。特に戦略コンサルティングファームや一部の外資系企業、総合商社、ITコンサル等で実施されており、思考力・構造化力・対話力といった「ビジネスの基礎体力」が問われます。
🔶ケース面接の目的とは?企業が見ている3つの視点
ケース面接が導入される背景には、企業が単なる知識量ではなく、思考の質や問題解決力のポテンシャルを評価したいという意図があります。特に戦略コンサルや外資系企業では、入社直後からプロジェクトにアサインされ、限られた時間で仮説を立て、クライアントに提案することが求められるため、ケース面接はそのシミュレーションとして「実務レベルで通用する素地があるか」を見極める場となっています。
企業が注視する主な観点は以下の3つです。
まず、論理的思考力。問題を要素に分解し全体構造を把握する力や、因果関係を整理して答えに近づく力が求められます。次に、仮説思考と柔軟性。情報が不完全な中で仮説を立て検証し、必要に応じて軌道修正する思考プロセスを言語化できるかが重要です。最後に、コミュニケーション力。考えを言語化して対話しながら進める能力や、相手と確認・調整しながら提案を作り上げる力が評価されます。
このように、ケース面接は単なる知識テストではなく、短時間で思考力と行動力の本質を観察できる機会として設計されている点を理解して臨むことが重要です。
▼初心者向けケース面接のコツ解説はこちらから
ケース面接の流れを完全解説!初心者が知るべきコツと合格するやり方 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🌟今すぐ実際の選考で出題されたケース面接の過去問を解いてみませんか?
CaseMatchは、『戦略コンサル内定者の3人に2人』が使っていた、ケース特化型AI面接練習サービスです。
✅ 完全無料・スマホでOK・24時間いつでも
✅ 1万件以上の回答データ×プロの評価から、あなたの回答を自動採点
✅また登録していると、コンサルや大手広告代理店などの【CaseMatch特別選考】にも挑戦できる!
👉今すぐケース面接の過去問を解いて、実力を測定してみませんか?

🔶どの業界で出る?ビジネス・IT・公共系の出題傾向の違い
ケース面接というと「コンサル特有の試験」と思われがちですが、近年では多様な業界で導入が進んでいます。特に「構造化された思考」「仮説ベースの提案力」「不確実性への対応力」が重要視される業界では、ケース面接を通じて受験者のポテンシャルを見極める傾向があります。
ここでは主な3業界──ビジネス系、IT系、公共系──における出題傾向と、求められるスキルの違いを解説します。
🔹 ビジネス系
最もオーソドックスなケース面接が行われる領域です。コンサルティングファームを中心に、「新規事業の立案」「既存事業の売上改善」「市場規模の推定」「競合分析」など、企業経営に直結するテーマが頻出します。
出題例:
・「日本の最大手書店の成長戦略を提案せよ」
・「あるカフェチェーンが東南アジアに進出する戦略を考えよ」
📝求められるのは、MECEな切り口での整理、論理的な思考展開、限られた時間内での意思決定力。また、数字感覚や市場への現実的な理解が求められるため、普段からニュースや業界動向を把握しておくことも重要です。
🔹 IT系(ITコンサル・SIer・DX推進企業など)
IT系のケースでは、技術的な背景を前提とした「課題解決型」の出題が多いのが特徴です。業務効率化・DX・AI導入などを切り口に、クライアント企業が直面する課題に対してソリューションを構築する力が問われます。
出題例:
・「地方自治体での業務プロセスをAIによって改善せよ」
・「製造業のクライアントに、クラウド移行を提案する際のポイントは?」
ビジネス知識に加えて、テクノロジーを使ってどう課題を解決できるかを論理立てて説明する力が重要です。SIerやITコンサルでは、ソリューションを「絵に描いた餅」で終わらせず、実装・運用面の現実性まで踏み込んで思考できるかどうかも評価の対象になります。
🔹 公共系(官公庁・公共政策系プロジェクト・NPOなど)
公共系のケースは、定量的な正解が存在しないテーマが多く、「価値観のバランス」や「利害調整力」が問われるのが特徴です。たとえば、「高齢者の社会的孤立を防ぐには?」「都市のごみ処理問題をどう解決するか?」といった課題に対して、住民・行政・企業など多様なステークホルダーの視点を踏まえた提案が求められます。
出題例:
・「小学校のいじめを減らすにはどうすればよいか?」
・「ある自治体での待機児童問題の解決策を考えよ」
この分野では、論理の一貫性以上に、視野の広さ・課題設定力・倫理的配慮が重要です。正解が一つではないからこそ、「なぜその打ち手を選んだのか」という納得感ある説明が求められます。
▼頻出パターンの解説はこちらから
【完全ガイド】ケース面接のお題&回答例|頻出パターンと攻略法を徹底解説! - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🔶ケース面接と通常面接の違いとは?
多くの就活生が最初に戸惑うのが、「ケース面接って普通の面接と何が違うのか」という点です。ガクチカや志望動機などを問う通常面接に慣れていると、ケース面接はその空気感や思考プロセス、回答方法がまったく別物に感じられるでしょう。面接官が評価するポイントもアプローチも大きく異なります。
✅面接官との関係性
通常面接は一問一答が基本ですが、ケース面接では面接官が議論の相手になります。仮説を述べればフィードバックが返され、追加情報も提供されることがあります。受験者には、自分の考えを言語化し、相手の反応に応じて柔軟に思考を進化させる力が求められます。
✅準備の方向性
通常面接は自己分析や志望動機、企業研究が中心ですが、ケース面接では「どんな問題でも構造的に考えられるか」「未知のテーマにも仮説ベースで対応できるか」が問われます。そのため、フレームワークの活用や仮説思考、論理的な話し方など、汎用的な思考スキルのトレーニングが必要で、場数とフィードバックが合否を分けます。
▼ケース面接の練習方法についてはこちらから
ケース面接はどう練習する?初心者でもできる対策方法&合格率を上げるコツ - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
📌 【例題で学ぶ】ビジネス系ケース面接の思考プロセス

🔶例題:国内で人気のカフェチェーンが東南アジア市場に進出する戦略を立てよ
「国内で人気のカフェチェーンが東南アジアに進出する戦略を立てよ」という一見シンプルなテーマの中に、実はケース面接特有の思考ポイントが数多く潜んでいます。
本記事では、初期の前提設定から現状分析、課題の絞り込み、具体施策の検討に至るまで、5分間で求められる思考の流れを丁寧に解説しています。フレームワークをなぞるだけでは見落としがちな“思考の深め方”を、リアルなシミュレーション形式でご体感いただけます。
▼本例題の内定者回答は以下の記事をご覧ください。
ケース面接の解き方を徹底解説|過去問を通して学ぶ“内定レベル”の思考vol1 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🔶例題:中規模テーマパークの売上向上
「何のためにフレームワークを用いているのか」を意識しながら論点設計そsるうのか、について解説しています。また本記事では、実際のお題を題材にGood回答とNG回答の例を取り上げています。実際に自分の回答と比べて、どのような点に差があるのかについて照らし合わせてみてください。
▼本例題の内定者回答は以下の記事をご覧ください。
ケース面接で評価される回答例とNGパターンを徹底比較 | 過去問を通して学ぶ“内定レベル”の思考vol2 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🔶ビジネス系ケースの例題8選
ケース面接対策は、インプットだけでなく実際に手を動かす練習が不可欠です。CaseMatchでは、実際にコンサルティングファームや大手事業会社で出題された問題を中心に、無料でケース面接を練習でき、自動でフィードバックも受け取れます。以下に、思考力を鍛えるのに最適なビジネス系ケースのお題をピックアップしました。
🌟以下のリンクから例題のケース面接を実際に練習することができ、またAIからの採点やFB、例題の解説を受け取ることができます。ぜひご活用ください!
【お題1】ペット業界の売上向上
https://casematch.jp/competition/bb2a3c11-e87e-4d1c-ba8a-1737e354ade7/
【お題2】交通機関の売上向上
https://casematch.jp/competition/ba42f874-2b1b-4b79-85ca-c9a8c6b62a63/
【お題3】家電業界の売上向上
https://casematch.jp/competition/d4463969-f527-419a-b977-a0280501198e/
【お題4】タクシー業界の市場規模推定
https://casematch.jp/competition/838b70d1-3216-49bb-8c33-fc9cc03d7c74/
【お題5】旅行業界の売上向上
https://casematch.jp/competition/d4da28d3-16b0-44c9-8dcd-c2486df6e41e/
【お題6】耐久消費財の売上向上
https://casematch.jp/competition/02505815-975e-4423-8049-c1303abda3b1/
【お題7】出版業界の売上向上
https://casematch.jp/competition/9eb47e60-362a-457b-918e-73033f84653b/
【お題8】アパレル業界の売上向上
https://casematch.jp/competition/d4e08c1a-a8da-4cd8-8688-55af5ca1b04e/
ケース面接は、数をこなす中で初めて「思考の型」が身についていきます。今回ご紹介したお題は、初学者から上級者まで幅広く対応できる内容です。ぜひ繰り返し取り組み、自分なりの仮説構築と伝え方を磨いてみてください。
🔶コンサルティングファームが求める「ロジカルさ」とは
コンサルティングファームがケース面接で最も重視する資質のひとつが「ロジカルさ」です。ただし、ここで言うロジカルさとは、“小難しい理屈を語れること”や“知識量が豊富なこと”ではありません。
限られた情報の中でも、筋道を立てて考え、自分なりの結論にたどり着けるか――この「思考の流れ」と「納得感」が最も大切にされます。では、具体的にどのような観点でロジカルさが評価されているのか。以下の3つに整理して解説します。
■① 情報を構造化し、因果関係で整理できているか
ロジカルな思考の出発点は、「情報の構造化」にあります。
例えば、「売上が減っている」という課題に対して、すぐに施策を考えるのではなく、「売上=客単価×客数」といった数式的な因果分解を起点に要素を洗い出すことが求められます。
このとき、要素をMECE(漏れなく・ダブりなく)に整理できているか、複雑な情報を単純な構造に落とし込めているかが評価の分かれ目です。構造化された視点で話せる人ほど、話の全体像が把握しやすく、面接官に「筋がいい」と感じさせます。
■② 仮説→検証の思考サイクルを自分で回せているか
ロジカルな受験者は、まず仮説を立て、それをもとに論点を絞り、必要な情報を引き出しながら検証していくという一連の思考プロセスを自然に回しています。面接中に、「まず◯◯という仮説を置いて考えてみます」と自らスタンスを明示できる受験者は、判断軸が明快で、議論の展開にも芯があり、評価されやすいです。
■③ 誰が聞いてもわかる“話し方”ができているか
意外と見落とされがちですが、コンサルの現場では「ロジカルであること=相手に伝わること」と同義です。つまり、いくら中身が論理的でも、聞き手の立場に立ってわかりやすく話せなければ、ロジカルとは評価されません。具体的には、「結論ファーストで話す」「理由や根拠を段階的に示す」「前提条件やスタンスを明示する」などの姿勢が重要です。
🏛 【例題で学ぶ】公共系ケース面接の難しさとは?

🔶例題:サッカーチームのケガ問題をどう解決する?
マッキンゼーの過去問をもとに構成された本記事では、「サッカーチームのケガをどう防ぐか?」という一見シンプルでありながら、構造的な仮説思考が求められるケースに取り組みます。思考の出発点となる仮説の立て方から、問いの設計、チームでの議論テーマの設計に至るまで、ケース面接で評価される思考の型を疑似体験できる内容です。
詳細はこちらの記事をご覧ください:【コンサル内定者が解説】マッキンゼー ケース面接の過去問にチャレンジ! - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🔶例題:迷子をどう減らすか?
ビジネスケースの「典型的な分析のフレームワーク」が適用できない点は公共系ケース特有の難しさです。本記事では「迷子をどう減らすか?」というシンプルなお題に対し、どのように論点設計をしていくかのプロセスについて解説しています。
詳細はこちらの記事をご覧ください:公共系ケース面接の難しさとは?|過去問を通して学ぶ“内定レベル”の思考vol3 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🔶公共系ケースの例題3選
公共系ケースでは、ビジネスケースのように「売上=客数×単価」など明確なフレームワークを用いることが難しい場面が多くなります。そのため、自ら論点を構造化し、関係者の視点や制約を踏まえて課題を特定していく柔軟な思考力が求められます。以下では、思考の幅を広げる3つの良問をご紹介します。
【お題1】食料に関する社会課題
https://casematch.jp/competition/821da44d-d9d2-4512-a693-71abf0e60591/
【お題2】働き方に関する社会課題
https://casematch.jp/competition/4f20bcb6-38d6-4d55-9371-2959218e2c8d/
【お題3】自立に関する社会課題
https://casematch.jp/competition/98685654-4c72-4bc0-a894-f152ab388b2e/
公共系ケースは“正解のない問い”に向き合うトレーニングに最適です。複数の立場を想定しながら課題を整理し、自分なりの仮説と論点を組み立てる経験は、どの業界を志望する方にも役立ちます。ぜひ実践を通じて、「構造を自分でつくる」力を鍛えてみてください。
🔶公共系で問われる「多様なステークホルダー視点」
公共系ケースにおいて、コンサルタントや面接官が特に重視するのが「多様なステークホルダーの視点を考慮できているか」という点です。ビジネスケースが基本的に「企業の利益最大化」を軸に思考を進められるのに対し、公共系の課題は「何をもって正解とするか」が明確に定まっていません。だからこそ、誰にとって・どのような価値をもたらすのかを常に問い直しながら進める、柔軟かつバランス感覚のある思考が求められるのです。
■ なぜステークホルダー視点が重要なのか?
公共政策や社会課題の解決に関わるテーマでは、「利害が一致しない複数の当事者」が必ず登場します。たとえば「通学路の安全対策をどうするか?」という問い一つとっても、
- 小学生本人(安全性を最重視)
- 保護者(安全と同時に利便性も重視)
- 学校(教育環境としての配慮)
- 地元自治体(予算制約と効果のバランス)
- 警察や交通インフラ担当部局(実現可能性と法律的整合)
など、関係者が多数存在し、それぞれが異なる視点や優先順位を持っています。このような構造の中では、単一の視点に立った「最適解」は存在せず、対立しうる意見を踏まえて、現実的かつ持続可能な打ち手を設計する力が問われるのです。
■ ケース面接での“浅い回答”とは?
公共系ケースでよくあるのが、「市民の満足度を上げるにはこの施策を打てばいいのでは?」といった単一視点・単一仮説の回答です。一見もっともらしく見えるものの、以下のような観点を欠いた回答は、面接官にとって「思慮が浅い」と受け止められることがあります。
- 他の当事者にどういう影響があるか?
- 利益相反が起きたとき、どうバランスを取るか?
- 施策の持続性や制度設計上の課題は?
- 実行主体は誰か?その人たちが動く理由はあるか?
このように、公共系ケースでは「思いつきの打ち手」ではなく、「関係者の構造を理解したうえで、納得感ある設計ができているか」が評価ポイントになります。
■ ステークホルダー視点の整理の仕方(フレーム)
複雑な構造を整理するために、以下のようなフレームを活用すると便利です。
① ステークホルダー列挙
まずは関係者を洗い出します(住民、行政、NPO、企業、学校、医療機関など)
② 利害と立場の可視化
それぞれのステークホルダーが何を優先しているのかを明らかにします。
例:
・住民…安全・生活の質
・自治体…コスト・成果指標・選挙対策
・NPO…理念との整合・支援対象との関係性
・企業…投資対効果・ブランド価値
③ 優先順位の判断軸を明確にする
どの視点に最も重きを置くべきか。短期と長期、緊急性と重要性、財政制約の有無などから絞り込みます。
④ 合意形成の方法を設計する
利害対立がある場合、それをどのように調整するか?ワークショップや意見交換会、社会実験を取り入れるなど、“プロセス設計”も含めた提案が望まれます。
■ 実際のケースにどう活かすか?
たとえば以下のような公共系テーマでは、上記のような整理が非常に有効です。
- 「高齢者の孤立を防ぐにはどうすべきか?」
→本人・家族・地域コミュニティ・自治体・医療機関の視点を統合- 「いじめを減らす教育政策を設計せよ」
→児童・保護者・教員・教育委員会・地域住民の関与- 「若者の自立支援に向けた就労支援プログラムを立案せよ」
→本人・行政・企業・NPO・家族など多層的な視座が必要
公共系の出題では、一見“抽象的”に見えるテーマを、どれだけ具体的な利害構造に落とし込めるかが実力の差につながります。
🧩例題を通して分かった“通過できる人”の共通点

ケース面接で高評価を得る人には、いくつかの共通した特徴があります。知識の量や業界理解よりも、「その場でどう考え、どう伝えるか」の質が問われているのです。特に、限られた時間の中で“正解探し”に走らず、仮説を立てて自走できるかが、結果に大きく影響しています。ここでは、通過者が実践していた思考スタンスを掘り下げていきます。
🔶「正解を出す」より「仮説を立てる」姿勢がカギ
ケース面接で落ちてしまう受験者の多くが陥るのが、「正しい答えを出さなければ」という思い込みです。もちろん、最終的な提案が現実的であることは大切ですが、面接官が見ているのは“答えの中身”より“そこに至る思考のプロセス”です。
📌つまり、正解かどうかではなく、「どう仮説を立て、どのように検証を進めようとしたか」が評価の中心にあります。
評価されるのは、その仮説が間違っていたときに「軌道修正ができるか」。仮説が否定されたとき、「では単価の方に原因があるかもしれませんね」と柔軟に考えを切り替えられる人は、思考の適応力が高く、実務でも重宝されます。
面接官は、「この人がコンサルタントになったとき、実際の現場で手がかりの少ない中でも前に進めるか」を見ています。だからこそ、“正解を探す人”より“前に進める人”が通過するのです。このような姿勢を身につけるには、「仮説を立てる練習」を重ねるしかありません。日頃から、「なぜそうなっているのか?」「他にどんな要因があり得るか?」を問い続けるクセを持つことが、ケース面接だけでなく、ビジネスにおける思考力全般の底上げにつながります。
🔶話し方・構成力・柔軟性の3点が差を分ける
ケース面接では「思考の深さ」だけでなく、それをいかに他者に伝え、議論の中で活かせるかが非常に重要です。
📝面接官は単に「頭が良さそうか」を見ているわけではなく、「この人と一緒にクライアントと議論できるか」「現場で通用するか」という観点で評価しています。
そのため、どれだけロジカルな思考をしていても、「話し方が曖昧」「構成がバラバラ」「問いかけに固まってしまう」といった状態では、評価が上がりづらいのが実情です。特に差がつくのが、以下の3つの力です。
■① 話し方(伝わる言葉選びとテンポ)
どれだけ論理的な考えを持っていても、それが伝わらなければ意味がありません。特にケース面接は限られた時間の中での対話形式なので、「結論から述べる」「話の区切りを明確にする」「専門用語や抽象語を使いすぎない」といった聞き手に配慮した言語化力が問われます。
たとえば、「競合優位性を検証します」ではなく、「今回は自社と競合を比較し、価格・ブランド・立地の3点でどちらに優位性があるかを整理します」と明確に話すことで、相手はあなたの思考に乗りやすくなります。
■② 構成力(考えを整理し、順序立てて伝える力)
話の構成がぐちゃぐちゃだと、せっかくの良いアイデアも伝わらずに終わってしまいます。評価される人は、全体の枠組みを提示してから詳細を語る、いわゆる「トップダウン型」の構成を自然に使いこなしています。
例:
「結論から申し上げると、価格戦略の見直しが必要です。理由は2つあります。まず1つ目に〜、次に〜」このように、聞き手にとって先が見通せる構成になっていれば、思考の筋道も評価されやすくなります。
■③ 柔軟性(問いかけや追加情報に応じて、即時に思考を修正できる力)
ケース面接では、面接官が途中で問いを変えたり、追加の前提を与えてくることがあります。こうした「想定外の変化」にうまく対応できる人は、実務での即応力や成長可能性が高いと評価される傾向があります。
柔軟性がある人は、「なるほど、そういう前提でしたら…」と一度自分の考えを置き直し、新たな条件で再構築できます。一方で、思考が固まっている人は戸惑い、黙り込んだり、最初の結論を無理やり正当化しようとして評価を落としがちです。
📝 ケース面接に受かる人がやっている練習法

ケース面接は“地頭勝負”と思われがちですが、実際には対策の質と量で大きく差がつく選考です。特に初学者ほど、「何から手をつけていいかわからない」と感じる場面が多いはずです。そこで本章では、未経験からでも実力を高められる練習ステップと、頻出テーマの押さえ方を解説します。思考力は才能ではなく、訓練によって確実に伸ばせます。
🔶ノー勉はNG?効果的な練習ステップと頻出テーマ
「ケースはその場の発想力勝負だから、練習しても意味がないのでは?」——そう考えて“ノー勉”で臨んでしまう人は、ほぼ確実に落ちます。なぜなら、ケース面接では「何を言うか」以上に「どう考えるか」の型(フレーム)が評価されるからです。未経験者がこの“考え方の型”を無意識に使いこなせるようになるには、段階的かつ反復的な練習が必要不可欠です。以下は、内定者の多くが実践していたケース対策の4ステップです。
■ STEP1|思考フレームの理解とインプット
まずはMECE、3C、4P、ファイブフォースなど、基本的な思考フレームをインプットします。ただし暗記ではなく、「どんな場面で、どう使うか」を理解することが重要です。たとえば市場推定では「面積×密度」、競合分析では「自社 vs 他社のKBF(Key Buying Factor)」というように、場面に応じた使い分けの感覚を養うことが第一歩です。
■ STEP2|構造的な回答プロセスの習得
ケースの良い回答は「結論→理由→分解→仮説→検証」という構造をなぞっています。これを身につけるには、過去問や練習ケースを用いて、「まず仮説を立てる→検証の筋道を組む→結論につなげる」という思考の流れを反復する必要があります。最初は一問15分程度の個人演習+自分の解答の言語化(書き起こし)をおすすめします。
■ STEP3|模擬面接・フィードバックの実践
個人練習だけでは、話し方や対話力、時間配分といった“アウトプットの質”は磨けません。実際に他者とやり取りする中で、自分の癖や弱点が見えてきます。CaseMatchのようなAIケース面接ツールや、就活仲間との模擬練習は、内定者がこぞって活用していた対策手段です。ここでは「話す順番」「問い返しへの対応」「構成の見せ方」が評価されるポイントです。
■ STEP4|頻出テーマに慣れる
ある程度フレームとプロセスが身についてきたら、出題されやすいテーマで場数をこなすことが重要です。以下は頻出テーマの一例です:
・市場推定(例:国内のタクシー市場規模を推定せよ)
・売上改善(例:地方百貨店の売上をV字回復させよ)
・新規事業立案(例:家電量販店がサブスクを始めるなら?)
・組織課題/人事戦略(例:若手社員の離職率を下げるには?)
・公共課題(例:若者の自立を促進するには?)
頻出だからこそ、「型」が通用しやすく、演習の効果も可視化されやすい領域です。ここで自信をつけることで、応用力のベースが固まります。
🔶通過者が使っていたおすすめ問題集・書籍
ケース面接対策では、思考フレームや問題の構造に慣れるための「良質な教材選び」も極めて重要です。特に内定者の多くは、独学だけでなく信頼性の高い問題集や書籍を繰り返し活用し、思考力の“型”を身体にしみ込ませていました。ここでは、実際に高評価を得た受験者が使っていた教材を厳選してご紹介します。
詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
▶【内定者が厳選】ケース面接対策に最適な本10選 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策
🔶模擬練習のやり方とフィードバックの受け方
ケース面接対策において最も効果が出やすいのが、「模擬練習+フィードバック」のサイクルです。インプットだけでは習得できない、対話の中での思考展開・伝え方・即応力といったスキルを実戦形式で磨くことができます。ただし、ただ場数を踏めばいいというものではありません。ポイントは“質の高い模擬練習”と“フィードバックの受け取り方”にあります。
■ 模擬練習の効果を最大化する3つのポイント
① 1人ではなく「他者と」練習する
ケースは対話形式の試験なので、1人で黙々と解いても限界があります。模擬練習では、自分の言葉で説明する力や、リアルタイムの思考修正、相手の反応を見ながら話す力が養われます。友人同士でロールプレイするだけでも、十分な効果があります。
② テーマを選ぶ前に「練習目的」を明確にする
ただ過去問を解くだけでは“解いたつもり”になるだけです。模擬前には「今日は結論ファーストを意識する」「今回は問いかけへの柔軟性を高める」といった目的を持ちましょう。目的があるだけで、練習後の振り返りの精度が格段に上がります。
③ 時間を区切り、実際の面接に近い形式で
実戦を想定し、15〜20分で制限時間を設けてアウトプットを出す練習を繰り返しましょう。考えながら話すプロセスに慣れておくことで、本番でのパフォーマンスも安定していきます。
■ フィードバックの受け方で“伸び幅”が変わる
模擬練習で最も重要なのが、客観的な視点からのフィードバックをどう受け止めるかです。内定者の多くが実践していた“伸びる人の姿勢”には、以下の特徴があります。
・「自分の主観」ではなく「相手がどう受け取ったか」を真摯に聞く
・防衛的にならず、指摘内容を一度すべて受け入れてみる
・その場で「どうすれば改善できるか?」を相談し、次の練習に反映する
また、フィードバックをもらった後は、録音・録画を見返す、メモにまとめる、言い換えて説明し直すなどのアクションをとることで、吸収率が大きく高まります。
■ CaseMatchなどのツールも活用を
AIと対話形式でケース練習ができるツール(例:CaseMatch)を活用すれば、時間がない時でも「仮説→構造化→結論提示→評価」を自動でフィードバックしてくれます。特に一人では練習相手が見つからない人にとっては、反復可能かつ定量的に改善点を可視化できる点で非常に有効です。
模擬練習は、“考える力”と“伝える力”をリンクさせる唯一の手段です。完璧な答えを出すよりも、「考える過程を言語化し、改善できる自分であること」をアピールする場として、練習の中に本番さながらの意識を取り入れていきましょう。
🏁 まとめ|本番で力を発揮するために準備すべきこと

ケース面接は、知識や経験ではなく、「その場でどう考え、どう伝えるか」が問われる試験です。だからこそ、本番で力を出し切るには、思考の型を身につけ、繰り返し練習を重ねることが不可欠です。正解を出すことより、仮説を持って一歩踏み出す姿勢が何より評価されます。地道な準備が、自信と納得感につながる最良の対策です。